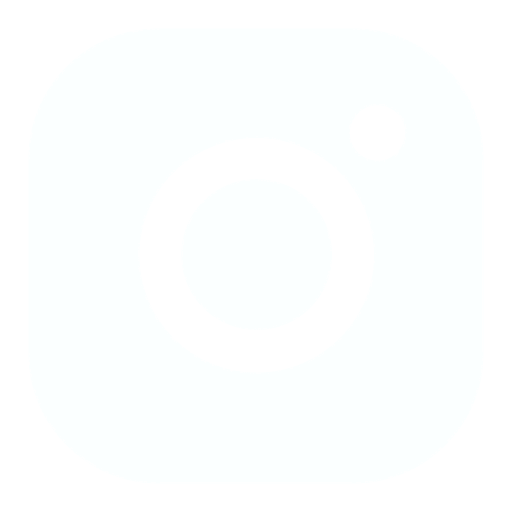✅ この記事でわかること
- ゲーム(VR・脳トレ・フィットネス系)の医療的活用の「エビデンス」と「可能性」
- リハビリ・認知症ケア・小児医療・精神科領域での活用イメージ
- 医療者が知っておくべきメリットとリスク
- 未来の医療・看護で期待されるゲーム活用の方向性
- 臨床・教育で使うときの具体的なポイントと注意点
本文中で用いるラベルについて
この記事では、医療・看護のYMYL領域としての信頼性を高めるため、
各記述のおおよその位置づけを次のラベルで示しています。
【エビデンス】
→ 論文・公的機関などの研究・一次情報に基づき、「そのような傾向を示した」と報告されている内容。
【実践レベル】
→ 病院・施設・現場の取り組みや実務での工夫など、主に実践報告や現場経験に基づく内容。
【まだ研究段階】
→ 研究開発中・試験導入中で、今後の検証やガイドライン整備が必要と考えられる内容。
いずれの記述も「すべての患者さんに必ず当てはまる」ことを意味するものではありません。
ゲーム活用はあくまで標準治療を補助する選択肢の一つとして捉え、個々の患者さんの状態や医師の方針を踏まえてご検討ください。
結論:ゲームは医療・看護を“補助的に支えるツール”になり得る
ゲームは「標準治療を置き換える手段」ではありません。
しかし、認知刺激・身体運動・注意転換・意欲の向上といった面で、医療やケアを補助する可能性が、いくつかの研究や実践報告から示されています。
ゲームの特性は大きく3つに整理できます。
- 楽しさによる自然な参加・継続【実践レベル】
義務感ではなく「やってみたい」と感じられることは、行動変容やリハビリの継続において重要です。 - 没入感・注意転換(ディストラクション)【エビデンス】
特にVRを用いた介入は、小児の痛みや不安から注意をそらす目的で活用されることがあります[1][2]。 - 成果の“見える化”【実践レベル】
スコアやレベルアップなど、小さな達成を積み重ねる設計は、セルフケアや運動習慣の継続と相性が良いとされています。
一方で、睡眠への影響・長時間利用・依存リスクなど、看過できないポイントもあります。【エビデンス】
したがって、ゲーム活用は「誰に・どんな目的で・どの程度使うか」を見極めながら、補助的なツールとして慎重に取り入れることが重要です。
医療・看護で使いやすい3つのゲームカテゴリ
① VR/ARゲーム:注意転換とモチベーション支援
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)は没入感が高く、
- 痛みや不安を一時的に和らげる「注意転換」[1][2]
- リハビリ動作への取り組み意欲の向上
といった目的で研究・実践が進められています。
活用が報告されている場面例【実践レベル】:
- 小児の採血・処置の不安軽減
- 手術前の恐怖感の緩和
- 脳卒中後リハビリの補助的ツール
- 高齢者のバランス練習の一部として
ただし、
- VR酔い(気分不良・めまい)
- 視覚障害やてんかん既往
- 機器の装着・脱着に伴う負担
などへの配慮が必須です。【エビデンス】対象の選定と観察を行いながら、「合う人に、合う形で」使う姿勢が求められます。
② 脳トレ・パズル系ゲーム:高齢者にも取り入れやすい認知刺激
【エビデンス】
脳トレやパズル系ゲームは、
- 注意力
- 処理速度
- ワーキングメモリ(作業記憶)
などの認知機能を刺激することを目的として、高齢者施設やデイサービスなどで活用されることがあります。
実践報告の中には、
- 「笑顔が増えた」
- 「参加意欲が上がった」
といったポジティブな声もあります【実践レベル】
認知症予防効果を断定するものではありません【エビデンス】。
従来のリハビリやケアと組み合わせた「楽しみながら取り組める活動」として位置づけるのが現実的です。
③ フィットネス系ゲーム:運動習慣を“続けやすくする”工夫として
リングフィットアドベンチャーやFit Boxingなどのフィットネス系ゲームは、
- 運動負荷を調整できる
- 座位モードなども選択可能
といった特徴があり、運動習慣づくりや軽いリハビリの補助として活用される場合があります【実践レベル】。
期待されるポイント【エビデンス/実践レベル】:
- 軽〜中等度の有酸素運動
- 体幹・下肢のトレーニング
- 自宅での運動継続のきっかけづくり
一部の回復期患者や地域在住高齢者を対象とした小規模研究で、バランス能力・歩行速度・下肢筋力の改善傾向が示された報告があります[3]。【エビデンス】
ただし、心疾患・転倒リスクの高い方では、医師やリハビリ専門職による事前評価が不可欠です。
あくまで「既存の運動療法・リハビリを補助するツール」として、無理のない範囲で取り入れることが推奨されます【実践レベル】。
ゲームが心身にもたらす主な影響(研究報告に基づく整理)
※以下は「そのような傾向を報告した研究がある」というレベルであり、万人に同じ効果が出ると断定できるものではありません【エビデンス】。
① 認知機能(注意・処理速度・判断力)【エビデンス】
アクション性のあるゲームや脳トレを用いた研究では、
- 注意の切り替え
- 視覚探索
- 反応速度
などの指標が改善したとする報告があります。
高齢者を対象とした小規模研究でも、脳トレによる処理速度の向上が示唆された例があります。
ただし、研究デザインや対象者により結果は異なり、認知症予防や治療として標準化された介入とは位置づけられていません。
あくまで、「認知機能を刺激する活動の一つ」として理解しておくのが適切です。
② 身体機能(バランス・歩行・体力)【エビデンス】
フィットネスゲームやバランスゲームは、一部の回復期患者や地域在住高齢者を対象とした小規模研究で、
- バランス能力
- 歩行速度
- 下肢筋力
の改善傾向が示された報告があります[3]。
対象者は選ばれており、すべての患者に画一的に適用できるわけではありません。
対象者選定・安全管理・リスク評価を行ったうえで、「リハビリの補助」として慎重に使うことが前提です。
③ メンタル(不安・ストレスの軽減)【エビデンス】
VRやゲームを使った介入では、
- 小児の処置時の不安
- 手術前の恐怖感
- 軽度のストレス
などの緩和に役立ったとする臨床研究が報告されています[1][2]。
一方、夜間の長時間プレイや生活リズムを崩すような利用は、睡眠の質低下や日中の倦怠感につながる恐れがあります。
「どの時間帯に、どのくらい行うか」という生活全体とのバランスを考えることが大切です。
④ コミュニケーションと動機づけ【実践レベル】
ゲームは世代を超えて楽しめる“共通の話題”になりやすく、
- 利用者同士の交流促進
- 医療者と若年患者の距離を縮めるきっかけ
として活用されることがあります。
また、「レベルアップ」「スコア」「実績」といったゲーム特有の要素は、
小さな成功体験 → 自分の変化を実感 → 行動の継続
という流れを支えやすい構造を持っています。
この点が、リハビリや生活習慣改善の支援にゲームが用いられる背景の一つになっています。
ゲーム×医療:国内外の実践例
① 長期入院患者のQOL支援【実践レベル】
長期入院患者にゲーム機を開放した事例では、
- 退屈感や孤独感の軽減
- 気分転換の機会の増加
- 他患者との交流のきっかけ
などが観察された報告があります。
ただし、QOL(生活の質)の指標との間に明確な因果関係があるとまでは言えず、さらなる研究が必要です。
現時点では、「選べる余暇の一つ」として提供する位置づけが妥当です。
② 回復期リハビリ・高齢者施設での活用【実践レベル】
回復期病棟や高齢者施設では、
- 脳トレゲームを用いたグループ活動
- バランスゲームを使った立位・歩行訓練の補助
などが行われています。【エビデンス】
Wii Fitのようなゲームを補助的に用い、バランス能力の改善傾向がみられた小規模研究もあります[3]が、対象は限定されている点に注意が必要です。
③ 認知症ケア【実践レベル】
認知症の方に対し、操作が比較的簡単なゲームを用いて「できた」という成功体験を重ねることで、
- 自尊心の維持
- 意欲の向上
- 笑顔や会話の増加
につながったとする実践報告があります。
一方、ルールが複雑なゲームは混乱やストレスを招くことがあり、その人にとって理解しやすく、負担にならない内容かどうかを見極めることが重要です。
④ 小児医療【エビデンス】
VR・ミニゲームを使った処置時の不安軽減は、複数の臨床研究で報告されています[1][2]対象年齢や環境によって効果の程度は異なり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
また、VR機器の装着そのものを怖がる子どももいます。
そのため、事前に本人・保護者と話し合い、安全面や心理的負担を一緒に確認しながら導入することが求められます。
⑤ 精神科領域【まだ研究段階】
精神科領域では、ゲームを活用した
- 感情理解・対処スキルの学習プログラム
- リラクゼーションやストレス緩和のためのコンテンツ
などが開発されています。
ただし、中等度以上のうつ病や依存傾向が強いケースでは、ゲーム利用が症状の悪化につながる可能性もあるため、専門職による評価と治療方針のもとで活用する必要があります。
ゲーム×医療の未来:技術進展がもたらす新しい選択肢
ゲーム技術や周辺テクノロジーは急速に進歩しており、医療・看護との連携も今後さらに広がる可能性があります。ここでは、研究・開発が進められている“近未来の方向性”を簡単に整理します。【まだ研究段階】
① 生体データと連動するゲーム体験【まだ研究段階】
心拍・呼吸・動作などの生体データをリアルタイムで取得し、
- 運動負荷を自動調整するフィットネスゲーム
- 不安や緊張の度合いに応じて内容が変化するVRプログラム
などを目指す研究が進められています。
これにより、個々の負荷や安全性に配慮したゲーム体験が実現しやすくなる可能性があります。
② 認知機能や情動の“可視化”【まだ研究段階】
AIや脳科学の進展により、
- ゲーム中の反応速度
- 選択の傾向
- ミスのパターン
などのデータから、認知機能やストレス状態の変化を推定しようとする研究も行われています。
将来的には、臨床判断を補助するツールの一部として活用される可能性があります。
③ 教育・研修の高度化【まだ研究段階】
看護教育・医療職向け研修の分野では、VRやシミュレーションゲームを用いて、
- 危険予知トレーニング
- トリアージの判断
- チーム連携・コミュニケーション
などを仮想環境で学ぶ教材開発が進んでいます。
実際の臨床現場では再現が難しい状況を、安全な環境で繰り返し体験できる点が大きな利点です。
④ “楽しみ”と“ケア”の境界がなめらかに【まだ研究段階】
技術が成熟するほど、
- 患者さんが「楽しみ」でゲームをしていたら
- 結果的にリハビリやセルフケアにもつながっていた
というように、「楽しみ」と「ケア」の境界が自然になめらかになる取り組みが増えていく可能性があります。
もっとも、これらの技術の多くは、現時点では研究段階または限られた場面での試験的導入にとどまっています。
広く臨床現場で活用するには、今後の検証やガイドライン整備、倫理・プライバシー・データ管理の議論が不可欠です。
看護実践でゲームを使うときのポイント
① コミュニケーションの“きっかけ”として【実践レベル】
ゲームを無理に勧める必要はありませんが、
- ゲームが好きな若年患者
- 昔の遊びやゲームの話題で盛り上がる高齢者
との関わりにおいては、共通の話題として有効なことがあります。
「最近どんなゲームをしていますか?」「こういう遊びは好きですか?」といった質問は、その人の価値観や生活背景を知るきっかけにもなります。
② 病棟レク・グループ活動への導入【実践レベル】
病棟レクやデイケアでゲームを導入する際は、次の点を意識します。
- 転倒・転落リスク(特に立位で行うゲーム)
- 画面の見やすさ・音量・照明
- ケーブル・機器の配置(つまずき防止)
- 認知機能や理解度に合ったルールの難易度
「誰もが無理なく参加できるか」を基準にゲームを選び、必要に応じてルールを簡略化するなどの工夫を行うと、安全で楽しい活動になりやすくなります。
③ 患者教育・セルフケア支援の補助として【実践レベル】
生活習慣病や心不全などのセルフケア支援に、ゲーム要素を取り入れたアプリやオンラインコンテンツが活用されることがあります。
看護師が患者さんに紹介する際には、
- 医師の治療方針と矛盾していないか
- 運動量や負荷がその人の状態に適しているか
- アプリの情報だけで自己判断しすぎないよう伝える
といった点を確認しながら、「役に立ちそうであれば一緒に活用方法を考える」という姿勢が重要です。
リスクと注意点
長時間プレイ・姿勢・環境【エビデンス/実践レベル】
ゲームの長時間利用は、
- 眼精疲労
- 頭痛・肩こり
- 不良姿勢の固定
などにつながることがあります。
推奨されるポイントは、
- 一定時間ごとの休憩
- 姿勢の確認・調整
- 適切な画面距離・照明
などをセットで案内することです。
睡眠・生活リズム【エビデンス】
特に就寝前のゲームや夜更かしを伴う利用は、
- 入眠困難
- 睡眠の質低下
- 日中の倦怠感や集中力低下
などにつながる可能性があります。
問診や面談の中で、ゲーム時間と生活リズムの関係をさりげなく確認し、必要に応じて「就寝前は控えめにする」などの工夫を一緒に考えることも看護の役割です。
ゲーム障害(Gaming disorder)への基本的理解【エビデンス】
WHOはICD-11でGaming disorder(ゲーム障害)を、
- ゲームのコントロールができない
- 他の活動よりもゲームを優先してしまう
- 日常生活や社会生活に支障が出る状態が一定期間持続している
場合に認められる概念として定義しています。
診断は専門医が行う必要があり、ICD-11の運用状況は国や地域によって異なります。
ゲームが好きであること自体は問題ではありません。
生活機能がどの程度損なわれているか、本人や周囲が困っているかが重要なポイントです。
医療者としては、心配なケースを見つけた際に、専門医や相談窓口につなげる「橋渡し役」を担うことが期待されます。
Q&A:よくある疑問
Q:高齢者でも安全に楽しめますか?
A:ルールが簡単で、座位で短時間から始められるゲームであれば、取り組める方も少なくありません。視力・聴力・認知機能・転倒リスクを確認しながら、無理のない範囲で行うことが大切です。
Q:病棟でゲームを導入することはできますか?
A:病棟レクやリハビリの補助としてゲームを使う例はありますが、機器管理・感染対策・安全管理など、施設ごとのルール作りが前提となります。導入前に多職種で話し合うことをおすすめします。
Q:ゲームに詳しくないスタッフでも運用できますか?
A:複雑なゲームである必要はありません。スタッフ同士で一度試してみて、「自分たちでも説明できる」「高齢者にも合いそう」と感じるシンプルなゲームから始めると、安全に運用しやすくなります。
まとめ:ゲームは「患者さんの力を引き出す小さな選択肢」
ゲームは、
- 認知・身体・気分への刺激
- コミュニケーションのきっかけ
- 行動変容のサポート
として活用できる、補助的なツールです。
一方で、リスク管理や適切な対象選びは欠かせません。
医療者がゲームのメリットと限界、リスクを理解したうえで取り入れることで、患者さんの「楽しい」「やってみたい」という気持ちを支える一歩になります。
ゲーム技術は今後も進歩し、“楽しさ”と“ケア”が自然につながる未来が少しずつ近づいています。
医療・看護の現場で、患者さん一人ひとりに合った形でゲームを適切に取り入れていくことが、これからのケアの選択肢を広げる可能性を持っています。
参考文献・参照資料(例)
※実際の公開時には、施設方針に合わせて適宜追加・変更してください。
- World Health Organization. Gaming disorder(ICD-11 解説ページ)
- Wong CL, et al. Virtual reality intervention for reducing pain and anxiety in pediatric venipuncture: randomized controlled trials. JAMA Netw Open.
- Ryu JH, et al. Use of immersive virtual reality in children for clinical procedures: a review. Frontiers in Medicine.
- Chen PJ, et al. Exergaming for improving balance and mobility in older adults: systematic review and meta-analysis.
- そのほか、国内外のリハビリ・高齢者医療・小児医療におけるVR/ゲーム活用に関するレビュー論文・ガイドライン など。