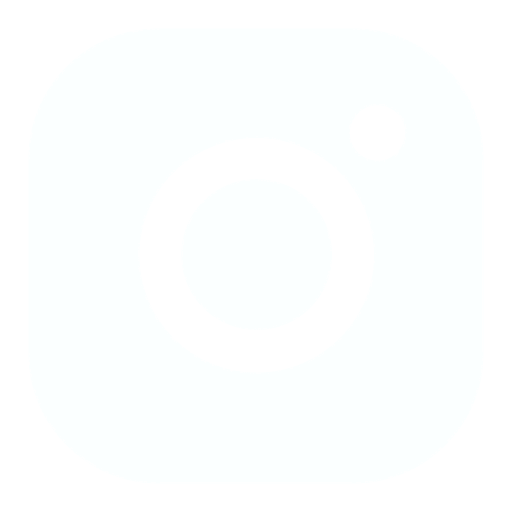はじめに|結論:効果的な研修は“状況に応じた選択”がカギ
「eラーニングと集合研修、結局どちらが良いのか?」これは多くの看護師や教育担当者が直面する悩みです。実は、“どちらが良いか”というよりも“どちらをどう使うか”が重要な視点です。
本記事では、現場の声や公的調査をもとに、それぞれのメリット・デメリットを整理し、研修目的に応じた最適な活用方法をご提案します。
集合研修のメリット・デメリットとは?
メリット:対面による相互作用とチーム連携の強化
集合研修の最大の利点は、参加者同士の相互作用によって「気づき」や「理解の深化」が生まれやすい点です。グループワークやロールプレイを通じて、実践に近い形で学べるため、特にコミュニケーションやチーム医療に関する内容に適しています。また、講師から直接フィードバックを受けられる点も魅力です。
デメリット:日程調整・場所確保・講師依存の課題
一方で、集合研修には物理的制約が多く、シフト勤務が基本の医療現場では日程調整が困難です。加えて、会場の確保や講師の手配といった運営負担も大きくなります。講師の質によって研修の成果が大きく左右される点も、安定した教育効果を求める場面では懸念材料となります。
eラーニングのメリット・デメリットとは?
メリット:時間・場所に縛られず学べる柔軟性
eラーニングの最大の利点は、スマートフォンやタブレットを活用することで、24時間いつでもどこでも学習できる点です。育児中や夜勤明けの看護師でも、スキマ時間を使って無理なく学べる環境を提供できます。また、同一コンテンツを繰り返し視聴できるため、理解度に応じた個別学習が可能です。
デメリット:学習意欲や理解度に個人差
一方で、自己学習であるeラーニングは、自律的な学習姿勢が求められます。集中力を保ちにくい環境では学習が進まないケースもあり、研修効果の測定やフォロー体制の整備が必要です。動画視聴だけで知識を定着させるには限界があるため、実践や確認テストと組み合わせた設計が重要です。
実際の現場の声:多くの施設がハイブリッド型を導入
厚生労働省の「医療従事者の教育に関する調査(2023年度)」などでも報告されている通り、多くの医療施設ではeラーニングと集合研修を目的に応じて併用する「ハイブリッド型研修」が主流となっています。
育成担当の声:目的別に使い分ける施設が多数
名古屋市内のある病院教育担当者はこう語ります:「感染対策などの全体共有が必要な内容は動画で。コミュニケーション研修などは対面で、と使い分けています。両方あることで、職員の学びを継続的に支えられます。」
【シーン別】おすすめの活用パターン3選
① 新人研修:集合研修+eラーニングのハイブリッド型
基礎的な知識はeラーニングで事前学習し、実技やチームワークは集合研修で補完することで、効率と定着率の両立が可能になります。
② 育休・復職支援:eラーニングで段階的にフォロー
育児などで一時離職していたスタッフには、復職前にスマホで受講できるeラーニングが有効。負担なく最新知識に触れられます。
③ 感染対策や法定研修:動画研修で全職員対応
医療安全研修、BLS研修、感染対策研修(特定行為研修含む)など、全職員が定期的に受講する必要のある内容は、eラーニングによる一斉受講が効率的です。履歴管理がしやすく、研修実施証明の発行も容易になります。
「集合研修+eラーニング」ハイブリッド化のメリット
研修負担の軽減+学習の定着率UP
看護師一人ひとりの時間的負担を軽減しつつ、集合研修の強みである「体験・実践的な学び」も取り入れることで、学習の質と定着度が向上します。
デジタル教材の活用で指導の質も標準化
講義動画やスライド資料をeラーニング化することで、研修内容の“標準化”が可能になります。これは、JNA(日本看護協会)の「新人教育ガイドライン」や病院機能評価の教育項目に準拠した教育体制づくりにも寄与します。講師の質に左右されない均質な研修の提供が、新人教育の属人化防止にもつながります。
よくある質問(FAQ)
Q:eラーニングだけでOJTは代替できますか?
A:OJTは実地での指導を含むため、eラーニングだけでは代替困難です。ただし、事前学習や復習として併用することでOJTの質を高められます。
Q:集合研修の代替はどこまで可能?
A:座学中心の内容であればeラーニングで代替可能です。ただし、実技や対人関係スキルが求められる内容では、集合研修を併用したほうが効果的です。
Q:研修効果の測定方法は?
A:理解度テスト・アンケート・受講履歴の記録などを活用し、定量・定性的に評価します。学習ログを可視化できるシステムの活用がおすすめです。
【まとめ】目的と現場に合った“最適な組み合わせ”を選ぼう
eラーニングと集合研修には、それぞれ異なる強みと限界があります。大切なのは「目的に合った手法を選ぶ」こと。研修を通じて得たい成果や、受講者の状況に応じて柔軟に組み合わせることが、これからの医療現場に求められる教育スタイルです。
🎁 無料ダウンロード特典あり
- 看護研修の「比較チェックリスト」
- eラーニング導入で成果を上げた施設事例
- 今すぐ使えるテンプレート資料つき!